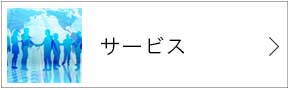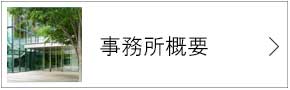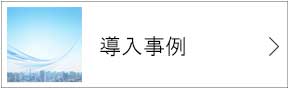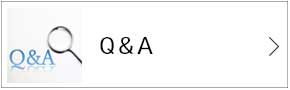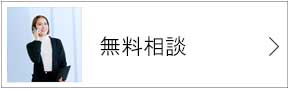入管関連最新情報2024年06月号

- 出入国在留管理局について(2024年05月現在)
- 東京入管の審査期間(2024年05月現在)
- 「不法就労外国人対策等関係局長連絡会議」が設置
- 短期入国者に渡航前審査を予定
- 在留資格に関する最新情報
- 法人顧客からのQ&A
1.出入国在留管理局について
1.東京入管の審査期間(2024年05月現在)
同月中のACROSEEDでの許可取得案件を2~3抽出し、その平均審査期間を表示しています。他社事例となりますので、あくまでも“めやす”としてご参照ください。
1,認定
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均22日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均29日
2.更新
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・52)…審査期間 平均62日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均57日
3.その他
・「高度専門職」への変更…審査期間 平均28日
2.「不法就労外国人対策等関係局長連絡会議」が設置
2024年5月16日、警察庁、法務省、出入国在留管理庁、厚生労働省の4省庁において「不法就労等外国人対策の推進(改訂)」が策定されました。
警察、入管局及び労働局による不法就労事犯・不法就労助長事犯の取締り等のための円滑な情報共有、外国人雇用状況届出情報の出入国在留管理庁及び入管局における積極的な活用などが「不法就労等外国人対策の具体的内容」としてあげられています。
3.短期入国者に渡航前審査を予定
ビザ申請が免除される日本への短期入国者を対象に、日本への渡航前審査の仕組み作りが進められています。
不法滞在者やテロリスの排除が目的で、アメリカのESTA(電子渡航認証システム)を参考に準備が進められており、2030年までの運用開始が予定されています。
2.在留資格に関する最新情報
1.高度人材(技人国・高度専門職)について
1.IT人材の在留資格の見直しが検討されています
東南アジアやインド始めとした優秀な若手人材の確保のため、法務省、経済産業省、文部科学省が連携し、現地大学との連携強化や在留資格の在り方も含め2024年度中に調査を行い、具体的な措置について検討を行うとされています。
また、留学生に対する戦略的なリクルーティングや奨学金の配分の重点化、大学間連携、国内外での日本人と外国人の学生が共に学ぶ環境の構築、国内就職を促進し、東南アジアとインド等を重点地域として、外国人留学生の受入数を2030年末までに36.5万人に拡大することを目指すといています。
3.法人顧客からのQ&A
- 弊社の外国人社員の1人で二重国籍者がいます。現在の在留資格は「日本人の配偶者等」ですが、A国とB国の2つの国籍を所持しており、在留カード上ではA国の国籍となっています。所用で海外に出国した際、日本への入国時にB国のパスポートを提示して入国したとのことですが、問題はないのでしょうか。また、日本への入国時に空港の入国審査官から「在留カードの裏面にB国の国籍も記載した方がよい」とのアドバイスを頂いたそうですが、このような対応をした方がよいのでしょうか。
- 二重国籍者の場合はイレギュラーな対応となりますのでケースバイケースで確認が必要ですが、原則として在留カードにA国、B国の両方の記載があればどちらのパスポートを提示して入国しても問題ありません。
また、在留カードへの2つ目の国籍の記載については、A国、B国の2冊のパスポートを出入国在留管理庁に持参すれば可能となっています。ただし、2国間のパスポートで氏名の記載等が同一でない場合は、出生証明書などにより同一人生を確認できる資料が必要となります。
日本への出入国時にはA国、B国の提示したいずれかのパスポートにしか出入国の記録が残りませんが、このようなケースでも原則として問題はありません。
とはいえ、入国審査官に事情を説明したり、何らかのトラブルに巻き込まれたときのことを考えると、A国、B国の両方のパスポートを所持することが望ましいと言えます。
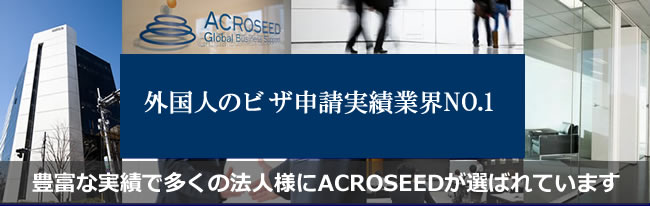
1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。